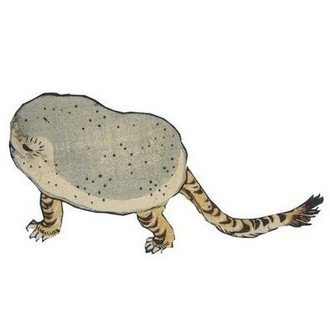江戸時代のウマが蹄鉄ではなく草鞋(わらじ)を履いていたという話
先日、歌川広重の「名所江戸百景 四ツ谷内藤新宿」をTwitterで紹介したところ、ウマが草鞋(わらじ)を履いているところが気になるという反応をいただきました。
案外、奇抜な構図が好きだった歌川広重。こちらは馬のお尻をアップにしています。広重は馬の足元にしゃがみこんで、町並みをスケッチしたのでしょうか。この場所がどこかは、オンライン展覧会「浮世絵動物園ー歌川広重「名所江戸百景」」(有料200円)にて紹介しています→https://t.co/Mbn5nxRpHX pic.twitter.com/9uSpsGPNpd
— 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art (@ukiyoeota) July 16, 2021
確かによく見ると、人と同じ様に、ウマも4つの足すべてに草鞋を履いていることが分かります。

ウマが草鞋を履いていることは珍しいのでしょうか。他の浮世絵も見てみましょう。こちらは同じく歌川広重の代表作「東海道五拾三次之内」より「吉原 左富士」。

街道の松並木を、ウマが3人の子どもを乗せて歩いています。3人乗りができるようにした鞍を「三宝荒神(さんぽうこうじん)」と呼ぶそうです。

ウマの足元を見てみましょう。草鞋を履いていることが分かります。私たちに分かりやすくしてくれているのでしょうか。左前足を上げて、草鞋の裏を見せてくれています。

次は葛飾北斎の浮世絵を見てみましょう。北斎の代表作「冨嶽三十六景」より「武州千住」です。

ウマが刈り取った草を背中に積んで、俯きながらゆっくりと歩いています。

こちらのウマの足元もアップで見てみましょう。やはり草鞋を履いていることが分かります。

ウマの足といえば、鉄製の「蹄鉄(ていてつ)」のことを思い浮かべる方も多いかと思います。家畜化された馬は蹄(ひづめ)が弱いため、蹄が痛むのを防ぐよう、蹄鉄を履かせているのです。
しかし、日本で蹄鉄が用いられるようになるのは明治時代に入ってから。江戸時代の在来種のウマは比較的蹄が強かったそうですが、荷物を運んだりする馬は、馬沓(うまぐつ)と呼ばれる草鞋を馬に履かせることで、馬の蹄が傷つかないようにしていたそうです。
ウマの足元をケアしてあげる様子が浮世絵に描かれています。こちらは溪斎英泉の「木曾街道板橋之駅」。「東海道五拾三次之内」のヒットに続いて制作された、英泉と広重の合作「木曽海道六拾九次之内」の一図です。

画面の右下を見てみましょう。ここは街道沿いにあるウマや駕籠を休ませるための休憩所。馬方の男性がウマの草鞋を履き替えさせています。

細長い草鞋と丸い草履がぶら下げられています。丸い方がウマ用の草履でしょうか。人間もウマも、長旅には新しい草履が欠かせません。

さらに、ウマの草鞋を履き替えさせている様子をしっかり描いた浮世絵もあります。歌川芳形の「東海道 藤沢」です。文久3年(1863)、徳川十四代将軍・家茂が京都に上洛する様子を題材としたとされる揃物です。

京都へと向かう行列から少し離れたところに、荷物を背負ったウマがいます。足元を見てみると、馬方の男性がウマの蹄を手入れしています。わざわざ行列を離れたのでしょう。何かウマの草鞋にトラブルがあったのでしょうか。

ウマが暴れないよう、優しく足首を掴み、泥を落としてあげています。左下に置かれている丸い形の草履が、ウマ用のものでしょう。男性はウマの様子を上目で伺いながら、丁寧にケアしています。胸元がはだけ、頭に鉢巻を巻くというちょっとヤンチャなファッションですが、ウマへの愛情はたっぷりな人のようです。単に、ウマに蹴られないように、注意をしているだけかもしれませんが。
以上、草鞋を履いているウマの浮世絵をご紹介しました。何気ない表現ですが、江戸時代における人間とウマとの結びつきが伝わってきますね。
追記:近子さん@WzRrG3uPpJvVmSF より、イザベラ・バードの『日本奥地紀行』で馬の草鞋の描写があるとご紹介いただきました。
1878年(明治11年)に日本を旅したイザベラ・バードの「日本奥地紀行」でも、蹄鉄ではなく草鞋を履いている描写があります
— 近子 (@WzRrG3uPpJvVmSF) July 17, 2021
文明開化時の日本の地方はまだ文明開化されておらず、イギリス人が見るアイヌの生活も面白かったです https://t.co/dxVa5u9dCk
イザベラ・バードは、世界各地を探検し、数多くの旅行記を執筆したイギリス人女性。明治11年(1878)に日本を訪れ、東京から日光、新潟を通り、日本海側から北海道まで旅行。さらに関西も旅し、『日本奥地紀行』を執筆しています。
栃木県日光市藤原の宿場町を出発し、西会津街道をウマに乗って新潟に向かっていた際、ウマの草鞋について詳細な記述を残しています。金坂清則氏による翻訳を引用します。
馬がはく草鞋は繋(つなぎ)のところで藁をねじって結んであるが、たいへんはた迷惑なものである。この「沓紐」はいつもほどけてしまうし、地面が軟らかくても二里[八キロ]しかもたず、地面が堅いとその半分さえももたない。また、これをはくために馬の足[の裏]はたいへん軟らかくふわふわなので、馬は草鞋なしではまったく歩けない。草鞋が薄くなるとよたよたし始める。すると〈馬子(マゴ)〉は不安になり、しばらくすると止まってしまう。そして、鞍にぶら下げてある水浸しの四足の草鞋を、足を優に一インチ[正しくは一〇インチ、二五センチ]もあげてなだめながらはかせるのである。これほどすぐに駄目になる上、扱いにくいものをよくも考え出したと思われる。馬の通る道には草鞋が散乱しており、子供たちはこれを拾い集めて積み上げている。腐らせて堆肥にするのである。一足が三、四銭もするので、どの村でも住民は暇な時間には草鞋作りをして過ごす。
―イザベラ・バード著・金坂清則訳『完訳 日本奥地紀行 1』平凡社、2012年。
ウマの草鞋は4~8㎞しかもたず、そのたびに草鞋を履き替えさせる必要があったそうです。そのため、予備の草鞋は必携でした。
この様子は、『日本奥地紀行』を漫画化した佐々大河『ふしぎの国のバード』2巻(KADOKAWA、2016年)の第8話「会津道①」でも描写されています。
明治初期の日本の地方の暮らしを記録した『日本奥地紀行』。現在の私たちから見ても、興味深い発見がいくつもあります。
文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)
いいなと思ったら応援しよう!