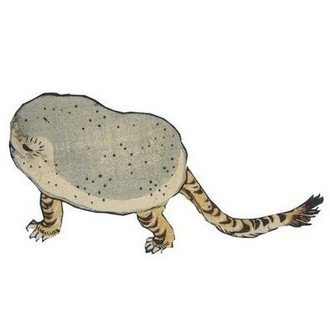弟子たちから見た歌川国芳はどんな顔?という話
歌川国芳は自身の姿をしばしば作品の中に描き込んでいます。例えばこちらの「名誉右に無敵左り甚五郎」は、名工である左甚五郎が歌舞伎役者の顔に似せた人形を彫っているという場面です。

しかしこの左甚五郎、国芳が好んだ閻魔のどてらを着て、芳桐印の入った手拭いを肩にかけていることから、国芳自身の姿が重ねられていると考えられます。国芳の大好きな猫がそばにいることからも、それは明らかでしょう。

ただ、国芳がこのように自分の姿を描く時はいつも後ろ姿で、顔を見せることがありません。
では国芳はどのような顔をしていたのでしょうか。今回は、国芳と直接面識があったどころか、弟子というこれ以上ない親しい関係にあった絵師たちによる国芳の「顔」をご紹介しましょう。
①落合芳幾の国芳像
まずは落合芳幾の「歌川国芳死絵」です。国芳が亡くなったのは文久元年(1861)。数え65歳の時でした。この作品は有名人が没した直後、追善や訃報の目的で制作された「死絵(しにえ)」と呼ばれる肖像画です。亡くなった日付や享年、戒名、墓所などが記されています。

歌川国芳が亡くなった時、落合芳幾は数え29歳。国芳との年齢差は36歳となりますので、芳幾にとって国芳は父親のような存在だったことでしょう。

しかもこの死絵は国芳が亡くなってすぐに制作されていますので、芳幾も国芳の顔をしっかりと覚えていたことは間違いありません。目元や口元のシワといった、晩年の国芳の風貌を丁寧に観察しています。今回紹介する作品の中で、最も本人そっくりに描かれた国芳の顔と言えます。
②月岡芳年の国芳像
次は、芳幾の弟弟子にあたる月岡芳年が描いた「歌川国芳肖像」です。こちらの制作は明治6年(1873)。国芳が亡くなってから12年が経った十三回忌の時に制作されたと考えられる肉筆画です。先ほどの芳幾の死絵は数多く量産される版画でしたが、こちらは貴重な一点物となります。

明治6年(1873)9月6日、両国の中村楼で、国芳の娘が会主となる書画会が催されました。落款に「於中村屋楼玉桜芳年画之」とあり、それを裏付けています。墨の線がスピードにのっていて、彩色が簡単なことから、お客を目の前にしてその場で仕上げたと推測されます。

最初に紹介した国芳の作品と比べてみますと、閻魔のどてら、肩にかけて手ぬぐいなど、雰囲気がよく似ています。

芳年と国芳の年齢差は42歳。芳年が数え12歳の頃に国芳に入門した時、国芳は54歳でした。芳年にとって国芳は父親よりもさらに年上の存在に感じられていたかもしれません。芳幾の真面目な死絵と比べて、国芳の顔がちょっと微笑んでいるような優しい表情に見えるのは、国芳を慕う芳年の気持ちがにじみ出ているからかもしれません。
そうそう、国芳の足元にカワイイ白猫が寄り添っていることをお見逃しなく。国芳が寂しくないように、芳年が添えてあげたのでしょう。亡くなってから12年も経ちますが、国芳の猫好きは当時の人々にとって深く記憶に残っていたようです。

ちなみに、国芳の十三回忌に合わせて「一勇斎歌川先生墓表」という石碑が建てられました。東京都墨田区向島2丁目にある三囲神社に現存しています。

この石碑について詳しくは、ARTISTIAN氏のブログで紹介されています。
③河鍋暁斎の国芳像
最後にご紹介するのは、河鍋暁斎の『暁斎画談』です。こちらは明治20年(1887)、河鍋暁斎が数え57歳の頃に刊行した本で、暁斎の幼少期のことが語られています。

暁斎は天保8年(1837)、数え7歳の頃に歌川国芳に入門します。この絵はその時の様子を描いたものです。部屋には国芳の門人たちがたくさんおり、取っ組み合いの喧嘩をしている者たちもいます。

左側にいる少年が幼い暁斎。目の前で国芳に絵を描いてもらっています。この時の国芳は数え41歳。人気絵師としての足場を固め、これからどんどんと活躍していこうとする時期でした。

顔はさらりと描いているため、顔の特徴がはっきり出ている訳ではありません。それよりもインパクトがあるのは、周りの猫たちでしょう。仕事中にも関わらず、国芳の懐に入っていたり、机の上に転がったりしています。この猫まみれの姿こそ、もっとも国芳の人となりを伝えていると言えるでしょう。
先ほど述べましたように、この絵は明治20年(1887)作です。暁斎は50年前の出来事を思い出しながら描いていることになります。しかも、国芳が亡くなってから26年も経っています。それでも暁斎の描いた国芳の姿がとても生き生きしているのは、幼い頃の国芳との出会いが、暁斎にとって強烈に印象に残っていたからでしょう。
以上、弟子たちが描いた国芳の肖像画を紹介しました。国芳の顔を思い浮かべながら国芳の作品を観賞してみると、また違った味わいが生まれるかもしれません。
歌川国芳を主人公とした、崗田屋愉一氏の漫画『大江戸国芳よしづくし』もぜひお読みください。
文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

いいなと思ったら応援しよう!