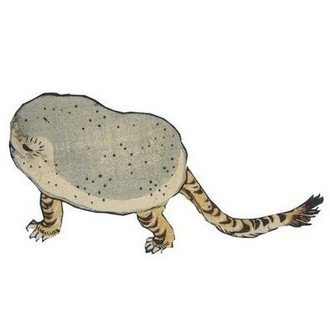ラスト・ウキヨエの継承者ー木版口絵を描いた絵師たち
太田記念美術館にて2021年5月21日~6月20日にて開催した「鏑木清方と鰭崎英朋 近代文学を彩る口絵―朝日智雄コレクション」展。明治20年代後半から大正初期、文芸雑誌や小説の単行本の巻頭に折り込まれた、木版口絵を紹介する展覧会でした。
はたして、木版口絵はどのような絵師たちによって描かれたのでしょうか。木版口絵研究の第一人者である山田奈々子氏の『増補改訂 木版口絵総覧』(文生書院、2016年)には112名の絵師の名前が挙げられていますが、ここでは、その中でも重要な役割を果たした絵師たち6名を、時代順に紹介していきましょう。
①武内桂舟
明治24年(1891)頃、小説の単行本において木版口絵というものが確立された際、最も重要な役割を果たしたのが、武内桂舟(たけうち・けいしゅう、1861-1943)です。
武内桂舟は、特定の師にはつかず、ほとんど独学で絵を学びました。もともと陶器の絵付けをしていましたが、後に挿絵画家に転向。尾崎紅葉率いる硯友社の小説家たちと親密に交流し、彼らが執筆した小説の口絵を手がけました。こちらは尾崎紅葉の小説『隣の女』の口絵。明治27年(1894)刊。

また、博文館の絵画部主任となり、明治28年(1895)創刊の『文芸倶楽部』という文芸雑誌の編集を指揮しながら、数多くの口絵を制作しました。こちらは『文芸倶楽部』第3巻第10編の口絵となる「美人撲蛍」。明治30年(1897)刊。

武内桂舟は、大正3年(1914)という、木版口絵がまもなく終焉を迎えようとする頃まで口絵を描き続けました。木版口絵の歴史を最初から最後まで見守り続けた、木版口絵の第一人者と言えるでしょう。
②富岡永洗
武内桂舟と同時期に活躍し、口絵の華やかな時代を形成したのが、富岡永洗(とみおか・えいせん、1864-1905)と水野年方(みずの・としかた、1866-1908)です。
富岡永洗は、狩野派の絵師である小林永濯に入門。小説の単行本や『文芸倶楽部』の口絵を手がけました。特に美人画を得意としており、官能的でありながらも卑俗にならない女性たちの艶やかさは、喜多川歌麿の再来とされ「明治の歌麿」と称されました。こちらは水谷不倒の小説『枯野の真葛』の口絵。明治30年(1897)刊。

③水野年方
水野年方は、月岡芳年の門人であり、鏑木清方の師匠にあたります。江戸時代から続く歌川派の流れを近代まで伝えたという点において、重要な役割を果たした絵師と言えるでしょう。
年方は、武者絵や美人画、戦争画といった、一枚摺の浮世絵版画でも人気を博しており、もともと小説の挿絵を描いたこともあって、早い段階から木版口絵の制作にも携わるようになりました。歌川派の浮世絵師として第一線で錦絵を描き続けていた実力は、木版口絵の中でもいかんなく発揮されています。こちらは小栗風葉の小説『恋慕ながし』の口絵。明治33年(1900)刊。

富岡永洗は明治38年(1905)、42歳で、水野年方は明治41年(1908)、43歳という若さでこの世を去ってしまいます。2人とも、木版口絵だけでなく、日本画の制作にも積極的でした。もう少し長生きしていれば、日本画家として高く評価され、現在でもその名前はしっかりと歴史に刻まれていたことでしょう。
④梶田半古
武内桂舟、富岡永洗、水野年方といった江戸時代生まれの絵師たちより、やや遅れて登場したのが梶田半古(かじた・はんこ、1870-1917)です。それほど年齢が離れているわけではないのですが、明治維新後の生まれというのが作風に影響を与えているのか、ハイカラで斬新なデザイン感覚に満ちています。
梶田半古は、浮世絵師の鍋田玉英や、南画家の石井鼎湖に入門するとともに、独学で菊池容斎の『前賢故実』を学んで、独自の画風を確立させました。明治19年(1886)に日本画家として出発しますが、明治30年(1897)頃から挿絵や口絵を積極的に手掛けるようになります。こちらは『文芸倶楽部』第11巻第13号口絵となる「菊のかをり」です。明治38年(1905)刊。女性の全身を大きく捉え、画面の枠で大胆にトリミングする感覚は、これまでの絵師にはなかったものです。

⑤鏑木清方
明治30年代末になると、富岡永洗、水野年方、梶田半古といった絵師たちが口絵の世界から退いていきます。そんな中、次世代を担ったのが、鏑木清方(かぶらぎ・きよかた、1878-1972)と、鰭崎英朋(ひれざき・えいほう、1880-1968)でした。2人とも、月岡芳年の系譜に連なっており、明治30年代後半から大正5年(1916)頃にかけて、木版口絵の最後の輝きを演出します。
鏑木清方は、月岡芳年の門人である水野年方に入門。新聞の挿絵を手がけ、明治30年代後半には、小説や文芸雑誌の口絵を担当するようになります。その清楚で気品あふれる美人画により、人気画家としての地位を確立しました。こちらは菊池幽芳の小説『百合子』後編の口絵です。大正2年(1913)刊。

鏑木清方は、明治40年(1907)頃から、展覧会に出品する日本画の制作に重きを置くようになり、大正6年(1917)以降には、挿絵や口絵の世界から遠ざかっていきます。
⑥鰭崎英朋
鰭崎英朋は、月岡芳年の門人である右田年英に入門。明治35年(1902)、尾崎紅葉の推薦により、春陽堂の編集局に入社し、雑誌や新聞の挿絵、小説の単行本の口絵を手掛けるようになります。特に大正初期には、鏑木清方と木版口絵の世界で人気を二分していました。清楚で華麗な清方の美人画に対し、英朋の美人画は妖艶な魅力を醸し出しているのが特徴です。こちらは柳川春葉の小説『誓』前編の口絵。大正4年(1915)刊。

肉筆の日本画の制作に専念していった鏑木清方に対し、英朋はそのまま挿絵画家としての生涯を全うしました。現在、清方の知名度が高いのに対し、英朋が忘れられた存在になってしまっているのは、英朋が大衆向けの挿絵画家であり続けたことが一つの要因でしょう。
以上、木版口絵を制作していた主要な絵師たち、6名をご紹介しました。
木版口絵は、当時の大衆から高い人気を集めていたものの、美術館に展示される日本画のような「美術」として認識されていませんでした。実際、水野年方や富岡永洗、梶田半古、鏑木清方のように、日本画家として評価されることを目指す絵師もいれば、武内桂舟や鰭崎英朋のように、口絵や挿絵の仕事を中心にし続けた絵師もいました。口絵に対する考え方は、絵師によってもさまざまだったのです。
木版口絵は、浮世絵研究の立場から、これまでほとんど注目されることはありませんでしたが、絵師たちの作画技術のみならず、彫師や摺師のテクニックも高い水準を誇っており、近代の日本美術を幅広い視点から捉えるためには、忘れてはならないジャンルなのです。
こちらの記事もどうぞ。
参考文献
文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)
いいなと思ったら応援しよう!